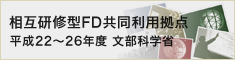2014年度のプログラム
2014年度文学研究科プレFDプロジェクト事前研修会
- 日時
- 2014年4月3日
- 場所
- 京都大学文学部第6講義室
- プログラム
-
- 第1部
- プロジェクトの全体像をつかむ
挨拶
文学研究科 教授 水谷雅彦
文学研究科プレFDプロジェクトの概要説明
文学研究科 准教授 伊勢田哲治、高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
昨年度の授業の様子
高等教育研究開発推進センター 特定助教 田中 一孝
プレFDプロジェクトに参加した先輩の声
文学研究科 教務補佐員 安井大輔・赤嶺宏介・佐金武
- 第2部
- 授業設計について知る
「授業のデザインの方法-ワークシートの活用-」
高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代
高等教育研究開発推進センター 准教授 田口真奈
- 第3部
- コースを考える
グループミーティング
2014年度の講義
前期講義リスト
| 哲学基礎文化学系ゼミナール I(木曜2限/文学部総合研究2号館地下1階第8講義室) | ||
| 4月10日、17日 | 太田 裕信 | 哲学の場所─日本において哲学することを考える |
| 4月24日/5月1日、8日 | 渡邊 一弘 | めくるめく懐疑論の世界 |
| 5月15日、22日、29日 | 満原 健 | 間文化哲学的視点から見た日本の哲学 |
| 6月5日 | 杉本 俊介 | 「倫理」とは何か:倫理学入門 |
| 6月12日、19日 | 須藤 英幸 | アウグスティヌスの「告白」と「三位一体論」─語り得ない神についての言明 |
| 6月26日/7月3日 | 藤田 俊輔 | ヤスパースとブーバーの人間存在論 |
| 7月10日 | 前期のまとめ | |
| 基礎現代文化学系ゼミナール I(木曜5限/文学部第1講義室) | ||
| 4月10日、17日、24日/5月1日 | 川嵜 陽 | 朝鮮における「皇民化」政策と朝鮮 |
| 5月8日、15日、22日、29日 | 佐藤 夏樹 | アメリカ社会とヒスパニック |
| 6月5日、12日、19日 | 坂 堅太 | 高度成長期の日本文学における労働者表象について |
| 6月26日/7月3日、10日 | 森下 達 | 戦後日本のポピュラー・カルチャーにおける核エネルギー表象 |
後期講義リスト
| 行動・環境文化学系ゼミナール II (後期/木5/文学部第7講義室 ) | ||
| 10月23日、30日 | 松谷 実のり | 移住と労働の社会学 |
| 11月6日、13日 | 石野 誠也 | 1.電気生理学的実験手法 2.神経細胞の情報符号化と脳部位間ネットワーク |
| 11月20日、27日 | 岩﨑 純衣 | 動物の「内省的能力」を探る(1,2)―比較認知研究からのアプローチ |
| 12月4日、11日 | 中園 智晶 | Brain-Machine-Interfaceをもちいた脳内情報表現の解析(1,2)―脳科学でこころは操作出来るか? |
| 哲学基礎文化学系ゼミナール II (後期/木2/文学部新4講義室) | ||
| 10月2日、9日、16日 | 太田 和則 | プラトンの世界観―「洞窟の比喩」を読む |
| 10月23日、30日/11月6日 | 太田 紘史 | 道徳心理学入門 |
| 11月13日、20日、27日 | 根無 一行 | 現代フランス現象学と宗教 |
| 12月4日、11日、18日 | 梅野 宏樹 | なぜ何も無いのではなく、むしろ何かがあるのか?―「存在の謎」入門 |
| 12月25日、1月8日 | 南 翔一朗 | 近代ヨーロッパにおける理性と信仰 |
| 1月15日 | 後期のまとめ | |
| 基礎現代文化学系ゼミナール II (後期/木5/文学部第1講義室) | ||
| 10月2日、9日、16日 | 大西 勇喜謙 | 科学的実在論論争入門 |
| 10月23日、30日/11月6日 | 岡内 一樹 | 森林からみる現代社会の歴史 |
| 11月13日、20日、27日 | 中山 俊 | フランスにおける文化遺産の保護 |
| 12月4日、11日、18日 | パク ミギョン | 妖怪と視覚文化 |
| 12月25日/1月8日、15日 | 柿本 真代 | 児童雑誌と子どもの近代 |
2014年度文学研究科プレFDプロジェクト事後研修会
- 日時
- 平成27年2月19日
- 場所
- 吉田南1号館
- プログラム
-
- 開会式
- 開会の挨拶
統括コーディネーター 文学研究科 教授 水谷 雅彦
司会:高等教育研究開発推進センター 特定助教 田中 一孝
- セッション1
- 自己紹介
参加者の自己紹介と公開講座を担当しての感想
- セッション2
- ビデオ視聴
講義ビデオの視聴
- セッション3
- 各系の授業の紹介
行動・環境文化学系 教務補佐員 安井 大輔
哲学基礎文化学系 教務補佐員 赤嶺 宏介
基礎現代文化学系 教務補佐員 佐金 武
- セッション4
- グループディスカッション
テーマ「深い学びを促す授業とは」
(3グループに分かれてディスカッション)
- セッション5
- ミニ講義
高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代
- セッション6
- 授業デザインの振り返り
ワークシートを用いた講義の振り返り
高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
- セッション7
- 全体ディスカッション
質疑応答&全体ディスカッション
司会:高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
- 閉会式
- 閉会の挨拶:文学研究科長 教授 川添 信介
修了証授与:高等教育研究開発推進センター長 教授 飯吉 透
情報交換会
文学研究科プレFDプロジェクトを振り返って
文学研究科統括コーディネーターから
本年度の総括コーディネーターを務めさせていただいたが、前任者同様、ほとんど何も貢献できることはなかった。というのも各系のコーディネーターの先生方や優秀な教務補佐員の皆さんに運営の実質をお任せしており、それで何の問題もなかった、というより極めて円滑な授業運営がなされていたからである。関係する方々に感謝したい。とりわけ教務補佐員の方々には、毎回の講義とその後のディスカッションに関する詳細な報告をメールでお届けいただき、それぞれの講義と議論の質の高さに毎回驚嘆できたことは幸いであった。講義担当者は、おそらく相当時間をかけて講義準備をされたのであろうが、いずれの講義も専任の教員になった将来において毎回の授業にこれほどの質を保つだけの準備をする余裕があるのだろうかといういらぬ心配をいだかせるほどのものであった。プレFDという京大文学部独自の試みが開始されて6年になる。開始時に思想文化学系の系代表として企画に手探りで参画した者としては、講義担当者が次々に自立した大学教員になっているという報を聞くにつけ感慨深いものがある。予算面を始めとして多くの問題が山積していることは事実であるが、あらためて関係各位のご協力をお願いする次第である。(文学研究科 教授 水谷 雅彦)
各系のコーディネーターから
今回初めてプレFDのコーディネーターとして参加しました。以前からプレFDのことは聞いており、コーディネーターや参加したポスドクたちからその経験について話してもらったことはあったのですが、今回実際に参加して非常に新鮮でよい経験をしたと思います。今回4人のプレFDの講義に参加し、6回の授業を聞いたのですが、どれも実に周到に準備されたよい授業だったと思います。もちろん、若い講師たちの勇み足や、ちょっとした思い込み、経験不足からくる緊張などはあるわけですが、それを補って余りある熱気があり、感動を受けました。授業のあとの講評も楽しい時間でした。それぞれの講師たちが自分の講義に生かそうと鋭いコメントを行うわけですが、自分が学ぶべき部分をほめ、気が付いた問題点を指摘するうち、あっという間に時間が過ぎました。講評を受けた講師は指摘された点を二回目の講義で十分に生かし、他の講師は自分の講義をするときに議論の内容を咀嚼して、準備しており、明らかに講義の質が上がっていました。これにはさまざまな準備の手伝いをし、講評の司会、まとめをしてくれた安井氏の貢献も大きかったかと思います。講師たちにもコーディネーターにも負担にはなりますし、特に教務補佐員の負担が大きすぎるのが問題かもしれません。が、プレFDは、それだけのコストを負担すべきよい制度であり、なんとか継続すべきであると思います。
(文学研究科 教授 田窪 行則)
小・中・高の教員とは異なり、大学では授業をするための訓練はこれまでほとんどなされてこなかった。私自身も大学院を出たばかりで非常勤講師をしたときは、大変苦労した記憶がある。このプレFDプロジェクトでは、講師は授業計画を綿密に立てて講義を実施し、終了後に学生や他の講師から講義の仕方について忌憚のないフィードバックを受ける。これは今後優れた授業をするための技法を身につけるまたとない機会となるだろう。コーディネーターとして参加した私自身、時間の割り振りや黒板の使い方やその他の授業手法について学ぶところが多々あった。また、古代哲学、道徳哲学、宗教哲学、形而上学など、各分野における最先端の内容を初学者にわかりやすく講義しようとするODたちの情熱に強く触発されもした。講師たちとコーディネーターにとって、このプレFDがたいへん有意義であることは間違いないだろう。後期は受講生が若干少ないのが残念であったが、みな若い講師たちの学問への情熱を受け取ったことと思われる。プレFDに参加した講師たちと学生たちの今後が楽しみである。
(文学研究科 准教授 児玉 聡)
変な話であるが、わたしは昨年まで2年間プレFD全体の統括コーディネーターを務めていたが、実は系のコーディネーターは一度もやったことがなかった。今回初めてこれを担当し、授業に毎回出席してフィードバックをするという作業を行うことになった。
基礎現代文化学系は所帯は小さいながらも多様な専修があつめられている。個人的には、顔は知っていても研究の内容は知らなかったというポスドクの方たちの研究内容の一端を知ることができた(しかも、まったく分野違いの方が私の研究と重なる関心を持っていることが分かった)のが今回系コーディネーターを務めての収穫であった。
授業のスタイルも、プレゼン用ソフトを華麗に使いこなす講師から、昔ながらのプリントアウトと板書というスタイルにこだわる講師まで多様だった。これは受講する学生にとっても変化があってよかったのではないだろうか。授業のやり方に一つの正解というものはないわけで、それぞれにいろいろなやり方を試す中から自分にあったやり方を見つけ、それを伸ばしていってもらえればと思う。このプレFDはそうした実験にはうってつけの場であるので、ぜひもっと大胆に活用していってもらえればと思う。
(文学研究科 准教授 伊勢田 哲治)
2014年度スタッフ
- 水谷 雅彦
- 統括コーディネーター
- 田窪 行則
- コーディネーター(行動・環境)
- 氣多 雅子
- コーディネーター(哲学基礎)
- 児玉 聡
- コーディネーター(哲学基礎)
- 永井 和
- コーディネーター(現代文化)
- 伊勢田哲治
- コーディネーター(現代文化)
- 安井 大輔
- 教務補佐(行動・環境)
- 赤嶺 宏介
- 教務補佐(哲学基礎)
- 佐金 武
- 教務補佐(現代文化)
- 飯吉 透
- FD研究検討委員会 委員長・高等教育研究開発推進センター長
- 松下 佳代
- 高等教育研究開発推進センター 教授
- 田口 真奈
- 高等教育研究開発推進センター 准教授
- 田中 一孝
- 高等教育研究開発推進センター 特定助教