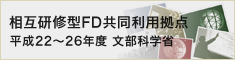2012年度文学研究科プレFDプロジェクト事前研修会
- 日時
- 2012年4月5日
- 場所
- 京都大学文学部新館
- プログラム
-
- 第1部
- プロジェクトの全体像をつかむ
挨拶
文学研究科 准教授 伊勢田 哲治
文学研究科プレFDプロジェクトの概要説明
文学研究科 教授 福谷 茂、高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
昨年度の授業の様子
高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之
プレFDプロジェクトに参加した先輩の声
文学研究科 教務補佐員 小城 拓理・田林 千尋・田中 一孝
- 第2部
- 授業設計について知る
「授業のデザインと振り返り-ワークシートの活用-」
高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代
- 第3部
- コースを考える
グループミーティング
2012年度の講義
前期講義リスト
| 行動・環境文化学系ゼミナールI(前期/木曜日1限/文学部第8講義室) | ||
| 4月26日 | 山﨑 瑤子 | 印欧語比較言語学とは ―データと方法論― |
| 5月10日 | 金京 愛 | 言語比較による発見・日本語の発見 |
| 哲学基礎文化学系ゼミナールI(前期/木曜日2限/文学部第4講義室) | ||
| 4月12日、19日、26日 | 濱崎 雅孝 | 哲学はキリスト教から何を学べるか? |
| 5月10日、17日、24日 | 千葉 清史 | カントの超越論的観念論 |
| 5月31日、6月7日、14日 | 中嶋 優太 | 「善の研究」の成立とその周辺 |
| 6月21日、28日、7月5日 | 永守 伸年 | 倫理学と信頼の問題 |
| 7月12日、19日 | 田中 一孝 | フィクションと感情 ―古代ギリシアにおける「芸術」理論 |
| 7月26日 | 前期の総括セッション | |
| 基礎現代文化学系ゼミナールI(前期/木曜日5限/文学部第1講義室) | ||
| 4月12日、19日 | 小野 容照 | 「野球」を通して考える朝鮮半島の近代 |
| 4月26日、5月10日 | 佐藤 夏樹 | ラティーノ像の形成 |
| 5月17日、24日、31日 | 稲葉 肇 | 原子の存在をめぐって |
| 6月7日、14日 | 網谷 祐一 | 理性と進化 |
| 6月21日、28日、7月5日 | 坂 堅太 | 戦後日本における文学と政治の関係について |
| 7月12日、19日、26日 | 吹戸真実 | 冷戦期アメリカ合衆国の中台政策と東アジア |
後期講義リスト
| 行動・環境文化学系ゼミナールI (木曜日1限/文学部第8講義室) | ||
| 10月4日、11日、18日 | 石井 和也 | 都市と地域の社会学 |
| 10月25日、11月1日、8日 | 富田 愛佳 | 言葉のフィールドワーク対・ルー語の実例 |
| 11月15日、29日、12月8日 | 川田 拓也 | コーパスを用いた言語研究−フィラーの分析を中心に− |
| 12月27日、1月10日 | 翁 和美 | 認知症の福祉の場の社会学 |
| 哲学基礎文化学系ゼミナール I 木曜日2限/文学部第4講義室) | ||
| 10月4日、11日、18日 | 杉本 俊介 | 『倫理』とは何か:ピーター・シンガーが巻き起こす論争 |
| 10月25日、11月1日、8日 | 古荘匡義 | 宗教について考える |
| 11月15日、29日、12月6日 | 薄井 尚樹 | 『相手を理解すること』を考える-デイヴィドソンを手がかりに |
| 12月13日、20日、27日 | 矢頭 英理子 | 近代の女性像 |
| 1月10日、17日 | 田鍋 良臣 | 『神話の哲学』入門 |
| 1月24日 | 後期の総括セッション | |
| 基礎現代文化学系ゼミナール I (木曜日5限/文学部第1講義室) | ||
| 10月4日、11日、18日 | 中尾 央 | 進化発生生物学の哲学 |
| 10月25日、11月1日、8日 | 川嵜 陽 | 朝鮮における『皇民化』政策と朝鮮 |
| 11月15日、29日、12月6日 | 富永 望 | イギリスから見た戦後天皇制 |
| 12月13日、20日、27日 | 大西 勇貴謙 | 科学的実在論論争入門 |
| 1月10日、17日、24日 | 山本 昭宏 | 戦後日本の核エネルギー認識の構築とその変容 |
2012年度文学研究科プレFDプロジェクト事後研修会
- 日時
- 平成25年2月14日
- 場所
- 吉田南1号館
- プログラム
-
- 開会式
- 開会の挨拶
高等教育研究開発推進センター長 教授 大塚 雄作
司会:高等教育研究開発推進センター 特定助教 田川 千尋
- セッション1
- 自己紹介
参加者の自己紹介と公開講座を担当しての感想
- セッション2
- ビデオ視聴
講義ビデオの視聴
- セッション3
- 講義の振り返り
ワークシートを用いた講義の振り返り
高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
- セッション4
- 哲学基礎文化学系の新しい試み
コンセプトマップ導入に関する事例報告
文学研究科 教務補佐員 田中 一孝
文学研究科 教務補佐員 田林 千尋
- セッション5
- ミニ講義「大学授業をどう創るか」
高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代
- セッション6
- ・グループディスカッション
テーマ1:「学生の多様性にどのように対応するのか」
テーマ2:「学生をどう授業に巻き込むのか」
テーマ3:「学びを促す授業デザイン」
・ミニミニ講義
テーマ1:文学研究科 教務補佐員 小城 拓理
テーマ2:高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
テーマ3:高等教育研究開発推進センター 特定研究員 坂本 尚志
・グループのまとめ
- セッション7
- 全体ディスカッション&まとめ
司会:高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
- 閉会式
- 閉会の挨拶:文学研究科長 教授 服部 良久
修了証授与:FD研究検討委員会委員長 教授 宮川 恒
情報交換会
文学研究科プレFDプロジェクトを振り返って
文学研究科統括コーディネーターから
2012年度も一年間プレFDをつつがなく行うことができた。このプロジェクトも4年目となり、ノウハウも十分に蓄積されて、すっかり安定してきた観がある。おかげで統括コーディネーターの私も大変楽をさせていただいた。もちろん、それは、このプロジェクトを支えた各系のコーディネーターの方々、教務補佐員のみなさん、プレFDプログラムに参加して研鑽されたODのみなさん、貴重なフィードバックをくれた学部生のみなさん、すべてのご協力があってのことである。感謝の意を表したい。このプログラムの将来だが、実は決して明るいとは言えない。京都大学全体の予算が縮小し、文学研究科も緊縮財政を迫られる中で、こうしたプロジェクトのための経費を捻出し続けることは容易ではない。しかし、実際に授業や事後検討会に参加してみて思うのは、当初想像していた以上にこのプロジェクトが参加者に大きな効果をもたらしているということである。現在の規模で続けていくことは難しいかもしれないが、何らかの形で継続的にこの取り組みが続くことを願ってやまない。(文学研究科 准教授 伊勢田 哲治)
各系のコーディネーターから
本プロジェクトは、3つの系が開講するゼミナールをプレFDの対象としており、それぞれの系を担当する文学研究科の教員が、コーディネーターとして各系の統括を行っています。ここでは、2012年度コーディネーターによる本プロジェクトの振り返りを示します。行動文化学系の今年度後期の入門ゼミナールでは、3人の講師により合計9回のプレFD授業が行われました。どの講師の方も、毎回の授業の反省を次回の授業に活かして努力されている様子がうかがえました。回数を重ねるにつれ、受講生の反応や様子を見ることも少しずつできるようになっているように思いました。また、他の人の授業を、受講する立場ではなく、授業する側として見学することは大変貴重な経験であることも、改めて感じました。
自分が受けてきたたくさんの授業、また、自身の授業経験を通して痛切に感じているのは、学生たちに伝えること、学生をインスパイアすることの大切さと難しさです。今年度、プレFDを体験された講師の方々には、さらにFDを超越するような存在感のある教師を目指していただけたらと願っております。
(文学研究科 教授 田中 和子)
このような授業が行なわれていることはまだ教員の間にもよく知られてはいないのではないかと思う。本年度コーディネーターとしてかかわってみて感じたのは、さすがは京大だな、ということである。講師として登場するODたちのなかには、大学の教壇に立つのはこれがはじめてという人も結構いた。もちろんご本人は眠れぬ前夜を過ごしたかもしれない。しかし参観している側からすると、皆さん達者で堂々とした先生ぶりだったというほかなかった。受講者も先生方の高水準の授業を熱心に聴講していた。私自身もいい勉強をしたという思いがいつものこった。こうなると授業後の検討会は自分の感想や疑問をすぐに講師やほかの参観者にぶつけられるありがたい場にはやがわりである。高等教育研究開発推進センターの先生方からはいつも新鮮な観点をお聞きすることができた。とかく「外圧」のように感じられがちのFDであるが、少なくとも京大ではそういうものにならないようにとなされている努力のひとつがこの「プレFD」だろうと思う。いちどぶらりと参観においでになっては、と先生方におすすめしたい。
(文学研究科 教授 福谷 茂)
かつて学生のアルバイトの定番といえば、塾講師と家庭教師であった。もちろん、他の職種よりも時給がよかったからである。しかし、講師業も長引くデフレの例外たりえず、たまに時給のよい講師の口があっても勉学に差し障るほどの激務であることが多いと聞く。そのようなわけで学生たちは講師業から離れていったが、このことは学生たちが「教師」の経験を持つ機会を失うことをも意味していた。「研究者」として生きていくために必要とされる「教師」としての技量を学外の社会で磨く機会が失われた以上、大学がそのような機能の一端を担わねばならない。プレFDが必要とされるようになった背景のひとつであろう。プレFDの授業担当者たちには、口うるさい京大生を納得させるという課題が課されるが、そこで必要とされる技量は、集中力のない中・高生に英文法を理解させるための技量と、存外共通点が多い。教師でも学生でもない「コーディネーター」という立場から授業を眺めて、改めて感じたことである。
(文学研究科 准教授 小野沢 透)
2012年度スタッフ
- 伊勢田 哲治
- 統括コーディネーター
- 田中 和子
- コーディネーター(行動・環境)
- 福谷 茂
- コーディネーター(哲学基礎)
- 小野澤 透
- コーディネーター(現代文化・前)
- 伊藤 和行
- コーディネーター(現代文化・後)
- 小城 拓理
- 教務補佐(行動・環境)
- 田林 千尋
- 教務補佐(哲学基礎)
- 田中 一孝
- 教務補佐(現代文化)
- 大塚 雄作
- FD研究検討委員会 委員長・高等教育研究開発推進センター長
- 松下 佳代
- 高等教育研究開発推進センター 教授
- 田口 真奈
- 高等教育研究開発推進センター 准教授
- 半澤 礼之
- 高等教育研究開発推進センター 特定助教
- 坂本 尚志
- 高等教育研究開発推進センター 特定助教
- 田川 千尋
- 高等教育研究開発推進センター 特定助教
- 吉田 裕子
- 高等教育研究開発推進センター 技術補佐