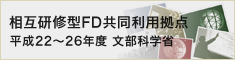2009年度文学研究科プレFDプロジェクト
本プロジェクトの概要
2009年度より、文学研究科と FD研究検討委員会が共同主催する「文学研究科 ODによる連続公開ゼミナールとその検討会」が始まりました。これは、いわゆる OD(オーバードクター)という正規ファカルティの予備集団のためのプレ FDプロジェクトであり、全国的にみても他に類例のない、きわめて先進的な試みであるといえます。具体的には、文学研究科の思想文化学科および現代文化学科に在籍するいわゆる ODが分担して、前後期各 3コマ(思想文化学科 2コマ、現代文化学科 1コマ)のゼミナールを実施し、そのすべてを公開としました。毎回の授業終了後、 20分程度の授業検討会を行い、授業の内容や形式に関して活発な意見交換を行いました。自らの教育を振り返り、自己を磨く良い機会となったと恩われます。また、これらの授業実施を受けて、前期 1回、後期 1回の計 2回、研修会を開催し、授業分担と研修会受講を条件として、参加者に総長名の修了証の授与をおこないました。このプロジェクトによって得た教えるという愉しみを、各自が将来に生かしていくことを期待しています。
(文学研究科長 芋坂 直行)
本プロジェクトに至った経緯と今後の展開
研究室出身の若い OD諸氏に学部生向けの入門リレー講義をお願いする。 OD支援策としては画期的なこの企画は、一方では「教歴の無い(浅い)講師による授業の質をいかに確保すべきか」という悩ましい問題をもたらしました。 OD支援と講義の質の確保との聞のこのジレンマを解くべく立案されたのが、今回のプレ FD事業です。授業の質が疑問視されている「新米教師」とは誰あろう、我々の元教え子です。我々には、彼ら彼女らの大学教師としての力量を高める責務がある。そのために大学における『教育実習」の機会を提供し、その中で授業の質の向上を図るべきではないか。プレ FDは、我々にこのような責任を自覚させるきっかけにもなりました。さらに以上の発想に潜む「上から目線」も、プレ FD活動に伴走する過程で修正を迫られます。若手講師諸氏の奮闘は、我々「非新米教師」にも、「いかに面白い授業を行うか」について改めて悩み模索する機会を与えてくれたからです。
(文学研究科 准教授 出口 康夫)
2009年度の講義
前期講義リスト
| 哲学基礎文化学系ゼミナール I (前期水1,文学部新6講) |
| 4月8日、15日 |
杉山 卓史 |
芸術分類論 |
| 4月22日、5月13日 |
相澤 伸依 |
セックスを哲学的に考える |
| 5月20日、27日 |
山口 雅広 |
なぜ「告白すること」が哲学的でありうるのか―アウグスティヌス『告白録』への招待 |
| 6月3日、10日 |
長田 蔵人 |
カントと自然神学の問題 |
| 6月17日、24日 |
今出 敏彦 |
ハンナ・アーレントの『人間の条件』再考―現代キリスト教思想の可能性を求めて |
| 7月1日、8日 |
佐々木 崇 |
テイラーの宗教論 |
| 7月22日、29日 |
山内 誠 |
悪の象徴系―ポール・リクールの象徴解釈学 |
| 哲学基礎文化学系ゼミナール II (前期木2,文学部新3講) |
| 4月9日、16日 |
鶴田 尚美 |
動物解放論 |
| 4月23日、30日 |
大月 栄子 |
キリスト教教義の成立と教父の思想 |
| 5月7日、14日 |
林 誓雄 |
「道徳感情論」入門―D. ヒュームとA. スミスの倫理思想 |
| 5月21日、28日 |
横田 蔵人 |
神の存在を証明する「五つの道five ways」―トマス・アクィナス『神学大全』から |
| 6月4日、11日 |
大西 琢朗 |
カリー・ハワード同型対応入門 |
| 6月25日、7月2日 |
田鍋 良臣 |
『存在と時間』入門 |
| 7月9日、23日 |
長谷川 琢哉 |
承認をめぐって |
| 代文化学 (前期金2,文学部新1講) |
| 4月10日 |
永井 和 |
授業の趣旨と現代文化学系の説明、および講師の紹介 |
| 4月17日、24日、5月1日、8日、15日 |
山口 育人 |
現代世界と国際通貨 |
| 5月22日、29日、6月8日、12日 |
冨永 望 |
戦後天皇制の出発 |
| 6月19日、26日、7月3日、10日 |
小林 敦子 |
革命芸術と芸術革命 |
後期講義リスト
| 哲学基礎文化学系ゼミナール III (後期水1,文学部新6講) |
| 10月7日、14日 |
吉沢 一也 |
現代におけるプラトンの『国家』 |
| 10月21日、28日 |
佐藤 慶太 |
「歴史の哲学」の歴史―20世紀初頭ドイツに焦点を絞って |
| 11月4日、11日 |
三宅 岳史 |
ベルクソンと神経学―科学万能主義とスピリチュアリスムの関係(19世紀後半フランス)の一例として |
| 11月18日、25日 |
守津 隆 |
西田幾多郎の哲学 |
| 12月2日、9日 |
堀川 敏寛 |
西洋思想と東洋思想の間、現代ユダヤ哲学の諸特徴―マルティン・ブーバーの対話思想を手がかりとして |
| 1月6日、13日 |
山本 圭一郎 |
帰結主義と非帰結主義 |
| 哲学基礎文化学系ゼミナール IV (後期木2,文学部新3講) |
| 10月1日、8日 |
田中 美子 |
詩人哲学者のひらめき |
| 10月15日、22日 |
川口 茂雄 |
物語る自己 |
| 10月29日、11月5日 |
中村 健 |
徳の倫理学 |
| 11月12日、19日 |
片上 茂樹 |
意識の発達段階について―ケン・ウィルバーの初期思想 |
| 11月26日、12月3日 |
小城 拓理 |
ジョン・ロック―その人と時代、そして哲学 |
| 12月10日、1月7日 |
水野 友晴 |
日本の哲学ことはじめ―「哲学」という訳語誕生の背景と明治の哲学 |
| 現代文化学 (後期月3,文学部新2講) |
| 10月5日、19日、26日 |
田中 泉吏 |
科学哲学への招待 |
| 11月9日、16日、30日 |
井上 治 |
近代日本と伝統芸道 |
| 12月7日、14日、21日 |
川嵜 陽 |
朝鮮における「皇民化」政策・戦争動員・言語 |
2009年度文学研究科プレFDプロジェクト前期研修会
- 日時
- 2009年7月15日
- 場所
- 吉田南1号館
- プログラム
-
- 開会式
- 開会の挨拶:FD研究検討委員会 委員長 教授 田中 毎実
司会:高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
- セッション1
- 自己紹介
参加者の自己紹介と公開講座を担当しての感想
- セッション2
- ビデオ視聴
講義ビデオの視聴
- セッション3
- 個人ワーク
ワークシートとリフレクションシートを用いた自分の講義の振り返り
解説:高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之
- セッション4
- 個人ワーク発表
- セッション5
- ミニ講義「大学授業をどう創るか」
高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代
- セッション6
- グループディスカッションのテーマ設定・グループ分け
- セッション7
- グループディスカッション
- セッション8
- グループディスカッション発表
- セッション9
- 全体ディスカッション
- 閉会式
- 閉会の挨拶:文学研究科長 教授 芋坂 直行
修了証授与:FD研究検討委員会委員長 教授 田中 毎実
情報交換会
2009年度文学研究科プレFDプロジェクト後期研修会
- 日時
- 2010年1月20日
- 場所
- 吉田南1号館
- プログラム
-
- 開会式
- 開会の挨拶:FD研究検討委員会 委員長 教授 田中 毎実
司会:高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
- セッション1
- アイスブレーキング 参加者の自己紹介と公開講座を担当しての感想
- セッション2
- ビデオ視聴
講義ビデオの視聴
- セッション3
- 個人ワーク
ワークシートとリフレクションシートを用いた自分の講義の振り返り
解説:高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之
- セッション4
- 個人ワーク発表
- セッション5
- 学生の声の紹介
受講生に対するインタヴュー結果の紹介
まとめと紹介:文学研究科FD支援特別研究員 井上 治・小城 拓理・三宅 宅史・中村 健
解説:高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之
- セッション6
- ミニ講義「大学授業をどう創るか」
高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代
- セッション7
- グループディスカッション
- 閉会式
- 閉会の挨拶:文学研究科長 教授 芋坂 直行
修了証授与:FD研究検討委員会 委員長 教授 田中 毎実
情報交換会