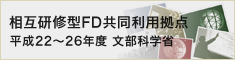2013年度のプログラム
2013年度文学研究科プレFDプロジェクト事前研修会
- 日時
- 2013年4月4日
- 場所
- 京都大学文学部新館
- プログラム
-
- 第1部
- プロジェクトの全体像をつかむ
挨拶
文学研究科 准教授 伊勢田 哲治
文学研究科プレFDプロジェクトの概要説明
文学研究科 教授 福谷 茂、高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
昨年度の授業の様子
高等教育研究開発推進センター 特定助教 田中 一孝
プレFDプロジェクトに参加した先輩の声
文学研究科 教務補佐員 小城 拓理・田林 千尋・佐金 武
- 第2部
- 授業設計について知る
「授業のデザインと振り返り-ワークシートの活用-」
高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代
- 第3部
- コースを考える
グループミーティング
2013年度の講義
前期講義リスト
| 哲学基礎文化学系ゼミナール I(木曜2限/文学部第4講義室) | ||
| 4月11日、18日、25日/5月9日 | 赤嶺 宏介 | 「入門」と「オリエンテーション」:カントによる哲学案内 |
| 5月16日、23日、30日/6月6日 | 山田 貴裕 | 意味論的実在論論争 |
| 6月13日、20日、27日 | 君嶋 泰明 | ハイデガー哲学入門―その初期の歩みから「存在と時間」まで |
| 7月4日、11日、18日 | 太田 裕信 | 京都学派と哲学 |
| 7月25日 | 前期のまとめ | |
| 基礎現代文化学系ゼミナール I(木曜5限/文学部第1講義室) | ||
| 4月11日、18日、25日 | 佐藤 夏希 | アメリカ社会とヒスパニック |
| 5月9日、16日、23 | 中尾 央 | 科学的総合の歴史と哲学 |
| 5月30日、6日、13日 | 大西 勇喜謙 | 科学的実在論論争入門 |
| 6月20日、27日/7月4日 | 吉川 絢子 | 植民地朝鮮における離婚訴訟 |
| 7月11日、18日、25日 | 田林 千尋 | 近代日本における歌謡研究について |
後期講義リスト
| 行動・環境文化学系ゼミナール II (後期/木5/文学部第7講義室 ) | ||
| 10月3日、10日 | 別役 透 | 「動物のナビゲーションに関する比較認知科学 |
| 10月17日、24日 | 平松 千尋 | 霊長類における色覚の機能と進化 |
| 11月14日、28日 | 北島 義和 | 農村アクセス問題とは何か―私的所有と公共の利益の挟間― |
| 12月5日、12日 | 西川 純司 | インフラストラクチャーの社会学―モノからみる社会 |
| 12月19日、26日 | 安井 大輔 | 多文化接触領域の食からみるエスニシティ |
| 1月16日 | 水野(藤井)英莉 | 生殖技術とジェンダー |
| 1月23日、30日 | 山内 熱人 | メキシコの農村文化とその生活 |
| 哲学基礎文化学系ゼミナール II (後期/木2/文学部新4講義室) | ||
| 10月3日、10日、17日、24日、31日 | 梅野 宏樹 | 悪いことばかりの世界に神なんかいない……のか? |
| 11月7日、14日、28日 | 末永 絵里子 | 考えることを考える―「問題系(プロブレマティック)」とは何か |
| 12月5日、12日、19日 | 岩井 謙太郎 | キリスト教思想入門 |
| 12月26日/1月9日、16日 | 上原 潔 | 宗教多元論とキリスト教 |
| 1月23日 | 上原 潔 | 後期のまとめ |
| 基礎現代文化学系ゼミナール II (後期/木5/文学部第1講義室) | ||
| 10月3日、10日、17日 | 冨永 望 | 京都市水道百年史 |
| 10月24日、31日/11月7日 | 川嵜 陽 | 朝鮮における「皇民化」政策と朝鮮 |
| 11月14日、28日/12月5日 | 坂 堅太 | 戦後日本の「労働」表象について |
| 12月12日、19日、26日 | 岡内 一樹 | 現代社会と環境との関係について |
| 1月9日、16日、23日 | 藤川 直也 | 存在しない者について語る―マイノング主義入門 |
2013年度文学研究科プレFDプロジェクト事後研修会
- 日時
- 平成26年2月20日
- 場所
- 吉田南1号館
- プログラム
-
- 開会式
- 開会の挨拶
FD研究検討委員会委員長 農学研究科教授 宮川 恒
司会:高等教育研究開発推進センター 特定助教 田中 一孝
- セッション1
- 自己紹介
参加者の自己紹介と公開講座を担当しての感想
- セッション2
- ミニ講義
「大学授業をどう創るか」
高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代
- セッション3
- ビデオ視聴
講義ビデオの視聴
- セッション4
- 講義の振り返り
ワークシートを用いた講義の振り返り
高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
- セッション5
- 教務補佐員から
文学研究科 教務補佐員 佐金 武
文学研究科 教務補佐員 赤嶺 宏介
文学研究科 教務補佐員 小城 拓理
- セッション6
- ・グループディスカッション
テーマ1:「学生の多様性にどのように対応するのか」
テーマ2:「学生をどう授業に巻き込むのか」
テーマ3:「学びを促す授業デザイン」
・ミニミニ講義
テーマ1:文学研究科 教務補佐員 小城 拓理
テーマ2:高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
テーマ3:高等教育研究開発推進センター 特定助教 田中 一孝
・グループのまとめ
- セッション7
- 全体ディスカッション&まとめ
司会:高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
- 閉会式
- 閉会の挨拶:文学研究科長 教授 服部 良久
修了証授与:高等教育研究開発推進センター長 教授 大塚 雄作
情報交換会
文学研究科プレFDプロジェクトを振り返って
文学研究科統括コーディネーターから
昨年に引き続き今年も総括コーディネーターを務めさせていただいた。とはいえ、昨年同様、私自身がしたことはほとんどない。各系のコーディネーターのみなさんと優秀な教務補佐員たちが運営の実質を担い、わたしはもっぱら勤務表の管理だけをさせていただいていた。今年度は年度途中でその教務補佐員の一人が都合により降板することになったが、これについても急遽経験者に交代していただくことができ、大きな問題は生じなかった。関係するみなさんのご協力に感謝したい。プレFDも5年を経て、過去の参加者の就職の話を聞くことも多くなった。「プレFDの経験が就職後役に立った」「面接の際にプレFDについて聞かれた」「教務補佐員をやっていたことが就職の決め手になった」など、このプロジェクトに参加したことがプラスに働いたという声を聞くたびに、いろいろ苦労がありつつもこのプロジェクトを続けてきてよかったと思う。
本プロジェクトは4年目までは本部からの援助を得て開催されてきたが、今年度からは援助が打ち切られ、文学研究科の内部の資金だけでやりくりしている。文学研究科自体の予算も削減される中でも今後もなんとか続けられるよう、このプロジェクトの意義について内外に広く訴えていければと思う。
(文学研究科 准教授 伊勢田 哲治)
各系のコーディネーターから
今年度のプレFDプロジェクトは後期の行動・環境文化学系ゼミナールⅡで実施しました。出席する学生は毎回40名以上で、それは最後の1月になってもほとんど減りませんでした。質問も少なからずあり、5限であるにも関わらずほぼ全員覚醒していることなどから、各回の講義が学生の興味を十分引き付けていることを、講義室の後ろでいつも実感していました。プロジェクトの講師は5名(各2回)でしたが、そうでない講師の何人かも検討会を希望しましたので、ほぼ毎回、講義後に検討会を開きました。そこでよくわかったことは、講師の皆さんがしっかり準備して講義に臨んでいること、そして講義内容と進め方について真摯に考えていることでした。当初は、生真面目な講師の皆さんが堅苦しく考えすぎることによって、どの講義も同じような構成と進め方になってしまうのではないかという懸念も持っていました。しかしそれは全く当たらず、講義はどれもきわめて個性的でした。そのことも学生の興味を引きつけ続けた理由の一つかもしれません。講義の質とは、単なる経験年数の関数として向上するものではなく、ひとえに講師の姿勢と個性に依存するものであるという、これまた当然といえば当然のことを、若い講師の皆さんから教えられた半年間でした。(文学研究科 教授 櫻井 芳雄)
小・中学校・高校の教員が授業をするためには大学でさまざまな訓練がなされているのに対して、大学の授業をするための訓練はこれまでほとんどなされてこなかった。大学院を出たばかりのODはずっとそのことに不安を感じていたように思う。実際初めて教壇に立った彼らから、授業の仕方について相談を受けたことがある。このプレFDプロジェクトは、そのような不安を取り除き、授業をするための技法を身につけるよい機会であった。今回参加したODから、口々に参加してよかったという感想を聞いている。初めてコーディネーターとして参加した私自身、長年大学の授業を担当してきたにも拘らず、時間の割り振りや黒板の使い方などをほとんど意識してこなかったことに気づかされたばかりか、授業準備にかけるODたちの情熱に強く触発された。授業後の検討会も、正反対の感想が出たりして、忌憚のない意見を交わすよい機会になっている。講師たちとコーディネーターにとって、このプレFDがたいへん有意義であることは間違いなかろう。他方、受講した学生たちにとってのこのプロジェクトの意義は、若い講師たちの学問への情熱を受け取ることであろう。学生たちの掛け値なしの本音を聞いてみたい気がする。
(文学研究科 教授 氣多 雅子)
大学教員という職に就いていると、学会等で発表や講演を聴く機会はありますが、他の人の通常の授業を見学することはまずありません。ましてや自分の専門外の分野の授業を見学する機会を見いだすことは不可能に近いのではないでしょうか。また若い人に授業を見学させてと頼んでもきっと嫌がられるでしょう。系ゼミのコーディネーターの仕事でもある授業見学は、専門外の分野に関する最新の研究状況を聞くというとても稀な機会でもあります。そういう点では、コーディネーターというのは意外とおいしい仕事なのかもしれません。
このようなことを書いたのは、文学部で系ゼミが始まって数年が経ち、これからの方向性を考えなければならない時期に来ていると思いますが、実際に系ゼミを見学したことのある教員の数はまだ限られているのではないだろうかと思ったからです。また近年多くの大学で教員募集の際には模擬授業が課される状況になっていることを考慮しますと、研究業績だけでなく、教育経験についても、どのように大学院生、そして若手研究者をケアしていくべきなのかということについて我々教員も考えなければならないのではないでしょうか。
(文学研究科 教授 伊藤 和行)
2013年度スタッフ
- 伊勢田 哲治
- 統括コーディネーター
- 櫻井 芳雄
- コーディネーター(行動・環境)
- 福谷 茂
- コーディネーター(哲学基礎・前)
- 氣多 雅子
- コーディネーター(哲学基礎・後)
- 伊藤 和行
- コーディネーター(現代文化・前)
- 永井 和
- コーディネーター(現代文化・後)
- 小城 拓理
- 教務補佐(行動・環境)
- 田林 千尋
- 教務補佐(哲学基礎)
- 赤嶺 宏介
- 教務補佐(哲学基礎)
- 佐金 武
- 教務補佐(現代文化)
- 大塚 雄作
- FD研究検討委員会 委員長・高等教育研究開発推進センター長
- 松下 佳代
- 高等教育研究開発推進センター 教授
- 田口 真奈
- 高等教育研究開発推進センター 准教授
- 田中 一孝
- 高等教育研究開発推進センター 特定助教