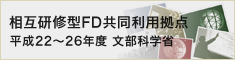2011年度文学研究科プレFDプロジェクト事前研修会
- 日時
- 2011年4月4日
- 場所
- 京都大学文学部東館
- プログラム
-
- 第1部
- プロジェクトの全体像をつかむ
スタッフの自己紹介
挨拶(文学研究科 教授 永井 和)
文学研究科プレFDプロジェクトの概要説明(文学研究科 教授 福谷 茂)
昨年度の授業ビデオ視聴(高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之)
プレFDプロジェクトに参加した先輩の声(文学研究科 教務補佐員 小城 拓理・田林 千尋・溝上 宏美)
- 第2部
- ミニ講義
「授業のデザインと振り返り-ワークシートの活用-」(高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代)
- 第3部
- 系ごとのディスカッション
評価基準について
コースデザインについて
2011年度の講義
前期講義リスト
| 哲学基礎文化学系ゼミナール I (木曜2限/文学部 新4講) |
| 4月21日、28日、5月12日 |
呉羽 真 |
心はどこにあるのか:認知哲学入門 |
| 5月19日、26日、6月2日 |
周藤 多紀 |
西洋中世における「嘘」:西洋中世言語思想入門 |
| 6月9日、16日、23日 |
杉本 俊介 |
「ビジネスにおける道徳」とはなにか:ビジネス倫理学入門 |
| 6月30日、7月7日、14日 |
鄭賢娥 |
1950年代日本のリアリズム絵画 - リアリズムの本質とその可能性 |
| 基礎現代文化学系ゼミナール I (木曜5限/文学部 新1講) |
| 4月14日、21日、28日 |
井上 治 |
近代日本における芸道思想の展開 |
| 5月12日、19日、26日 |
川嵜 陽 |
植民地朝鮮と戦争動員 |
| 6月2日、9日、16日 |
佐藤 夏樹 |
ラティーノアイデンティティの形成 |
| 6月23日、30日、7月7日 |
溝上 宏美 |
イングランドの女性は移民をどうとらえたか? - 多文化化するイギリスと自国像の変容 |
| 7月14日、21日、28日 |
網谷 祐一 |
理性と進化 |
後期講義リスト
| 行動・環境文化学系ゼミナール Ⅱ (木曜1限/総合研究2号館 第8講義室) |
| 10月6日、13日 |
松本 亮 |
言語類型論(1)・(2) |
| 10月20日、27日 |
江南 健志 |
山村の社会学(1)・(2) |
| 11月10日、17日 |
シルビア・スタニアク |
意味論と語用論(1)・(2) |
| 12月1日 |
山本 理子 |
アジアの主婦とメイド雇用(1) |
| 12月8日、15日 |
林 由華 |
言語のマイノリティ、マジョリティ(1)・(2) |
| 12月22日 |
翁 和美 |
認知症患者の社会学(1) |
| 12月27日 |
山本 理子 |
アジアの主婦とメイド雇用(2) |
| 1月12日 |
翁 和美 |
認知症患者の社会学(2) |
| 1月19日、26日 |
森田 次朗 |
オルタナティブ・スクールを事例とした社会学(1)・(2) |
| 2月2日 |
宋 基燦 |
在日コリアンの民族教育 |
| 哲学基礎文化学系ゼミナール Ⅱ (木曜2限/文学部 新館 第4講義室) |
| 10月13日、20日、27日 |
田中 一考 |
古代ギリシアにおける文芸理論と「芸術」思想 |
| 11月10日、17日、12月1日 |
日高 明 |
「純粋経験」の意義:西田哲学入門 |
| 12月8日、15日、22日 |
田鍋 良臣
古荘 匡義 |
現象学運動の展開と宗教哲学 |
| 1月5日、12日、19日 |
濱崎 雅孝 |
「神は死んだ」のか? - ポストモダンのキリスト教 |
| 基礎現代文化学系ゼミナール Ⅱ (木曜5限/文学部 新館 第1講義室) |
| 10月13日、20日、27日 |
杉本 舞 |
「世界最初のコンピュータ」とは?コンピューティング史入門 |
| 11月10日、17日、12月1日 |
中尾 央 |
規範と罰の進化について |
| 12月8日、15日、22日 |
富永 望 |
イギリスから見た戦後天皇制 |
| 1月1日、19日、26日 |
小野 容照 |
「野球」を通して考える朝鮮半島の近代 |
2011年度文学研究科プレFDプロジェクト事後研修会
- 日時
- 平成24年2月23日
- 場所
- 吉田南1号館
- プログラム
-
- 開会式
- 開会式
開会の挨拶:FD研究検討委員会委員長 教授 田中 毎実
司会:高等教育研究開発推進センター 特定助教 田川 千尋
- セッション1
- 自己紹介
参加者の自己紹介と公開講座を担当しての感想
- セッション2
- ビデオ視聴
講義ビデオの視聴
- セッション3
- 講義の振り返り
ワークシートを用いた講義の振り返り
高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
- セッション4
- 学生の声の紹介
受講生に対するインタヴュー結果の紹介
文学研究科 教務補佐員 小城 拓理・田林 千尋・溝上 宏美
高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之
- セッション5
- ミニ講義「大学授業をどう創るか」
高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代
- セッション6
- ・グループディスカッション
テーマ1:「学生の多様性にどのように対応するのか」
テーマ2:「学生をどう授業に巻き込むのか」
テーマ3:「学びを促す授業デザイン」
・ミニミニ講義
テーマ1:高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
テーマ2:高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之
テーマ3:高等教育研究開発推進センター 特定研究員 坂本 尚志
・グループのまとめ
- セッション7
- 全体ディスカッション&まとめ
司会:高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
- 閉会式
- 閉会の挨拶:文学研究科長 教授 佐藤 昭宏
修了証授与:FD研究検討委員会委員長 教授 田中 毎実
情報交換会
文学研究科プレFDプロジェクトを振り返って
文学研究科統括コーディネーターから
もともと文学部はFDという発想にはなじまないところだった。元来が少人数教育の場であり、技術的な問題を度外視してしまうのが文学部的だったのである。研究者としての自覚が教育者としての自覚をうまく育てなかった。またそれでよしとしてきたのが文学部である。
こうしたなかFDが、しかもよそに例のないプレFDという携帯で文学部を舞台にして毎年実施されているのは、初年度において制度設計をされた文学部側出口康夫先生と高等教育研究開発推進センターの先生方の英知の賜物であり、日々の運用を支えてくれる教務補佐員たちの有能さのおかげだというほかない。縁あって初年度以来見守ってきた私にとっては自分にもっとも欠けているものに直面する思いであった。真剣に準備し授業するODたち、かなり難しい講義に「先輩を鍛える」ために出席し、毎回リフレクション・シートを書き、時にはインタヴューに応じる学部生たち、これはなかなか感動的な光景である。ぜひ参観していただくことをお勧めする次第である。
(文学研究科 教授 福谷 茂)
2010年度文学研究科プレFDプロジェクト〜プロジェクト2年目を迎えて
2009年度から始まった本プロジェクトも二年目を迎えました。本年度からは、思想文化学系、現代文化学系に加え、新たに(社会学・心理学・言語学・地理学の各専修を擁する)行動文化学系も加わり、これら三つの系がそれぞれ開講する「系ゼミナール」、即ち「OD(オーバードクター)リレー講義」がプレFDの対象となっています。二年目に入り、「公開授業+授業後の検討会+半期に一度の研修会」というプレFDのメニューもしっかり定着しつつあります。また本年度のプレFDを現場で支えてくれているのは、本研究科の特別研究員たちですが、彼女ら/彼らは、いずれも昨年度のプレFD体験者です。プレFDの一参加者から、それを運営する側へ。文学研究科プレFDからは、未来の「FD活動の担い手たち」も着実に育ちつつあるのです。
(文学研究科 准教授 出口 康夫)