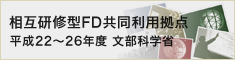2010年度の講義
前期講義リスト
| 行動・環境文化学系ゼミナール I (木曜1限/文学部 新6講) | ||
| 4月8日、15日 | 松野 響 | 動物の視知覚について |
| 4月23日 | 浅田 晃佑 | 発達心理学(子どものコミュニケーション能力の発達1) |
| 5月7日 | 浅田 晃佑 | 発達心理学(子どものコミュニケーション能力の発達2) |
| 5月14日 | E. Evseeva | 理論言語学(言語学の諸分野・卒業論文のテーマの選び方など) |
| 5月21日 | E. Evseeva | 理論言語学(不定表現の分析;理論言語学の諸分野における分析方法) |
| 5月27日、6月3日 | 田村 早苗 | ことばの意味を捉える:日本語の時制分析から |
| 6月11日 | 濱西 栄司 | 社会学方法論(集合行為/社会運動研究) |
| 6月18日 | 濱西 栄司 | 社会運動の社会学(グローバル化と「新しい公共」) |
| 6月24日、7月1日 | 朝田 佳尚 | 社会問題を斜めから見る −社会学は監視カメラの広がりという現象をどう捉えるか |
| 7月9日 | 木村 至聖 | 文化遺産の社会学:その理論的背景 |
| 7月16日 | 木村 至聖 | 産業遺産のフィールドワーク:「軍艦島」を事例として |
| 哲学基礎文化学系ゼミナール I (木曜2限/文学部 新4講) | ||
| 4月8日、15日、22日 | 藤田 大雪 | 原因」とはなにか-ギリシャ哲学と現代 |
| 5月6日、13日、20日 | 大西 琢朗 | フレーゲの論理主義-「数学の哲学」入門 |
| 5月27日、6月3日、10日 | 太田 徹 | 「自律」とはなにか-カント哲学入門 |
| 6月17日、24日、7月1日 | 杉山 卓史 | 芸術分類論-「美学」入門 |
| 7月8日、15日 | 辻内 宣博 | 西洋中世における自然学−中世思想入門 |
| 基礎現代文化学系ゼミナール I (木曜5限/文学部 新7講) | ||
| 4月9日 | 永井 和 | オリエンテーション |
| 4月15日、22日 | 冨永 望 | 戦後天皇制の出発 |
| 5月6日、13日 | 鹿 雪瑩 | 自民党内親中派と戦後の日中関係 |
| 5月20日、27日 | 溝上 宏美 | 歴史を通じて移民問題を考える-イギリスを事例に |
| 6月3日、10日 | 佐藤 夏樹 | ラティーノアイデンティティの形成 |
| 6月17日、24日 | 有賀 暢迪 | 18世紀ヨーロッパの科学と文化・思想 |
| 7月1日、8日 | 中尾 央 | 文化進化論について |
後期講義リスト
| 行動・環境文化学系ゼミナール I (木曜日 1時限 文学部 新6講) | ||
| 9月30日、10月7日 | 柴田 陽一 | 地理的表象からみる京都の近代 |
| 10月14日、21日 | 福浦 一男 | タイの宗教と社会 |
| 10月28日、11月4日 | 佐々木 祐 | 地域に生きる人々:先住民について |
| 11月11日、11月18日 | 金 京愛 | 言語を対照することによる発見:日本語を見直す |
| 11月25日、12月2日 | 安部 麻矢 | フィールドワークの言語学 |
| 12月9日、16日 | 中村 千衛 | 文法的『性』について |
| 1月13日、20日 | 渡辺 創太 | 様々な動物の錯視について |
| 1月27日、2月3日 | 田邊 亜澄 | 視覚認知の情報処理と視覚的意味と記憶 |
| 哲学基礎文化学系ゼミナールⅠ (木曜日 2時限 文学部 新4講) | ||
| 10月7日、14日、21日 | 佐々木 拓 | 自由意志と決定論の問題 |
| 10月28日、11月4日、11日 | 佐金 武 | 時間概念の探求:現在主義の観点から |
| 11月18日、25日、12月2日 | 城阪 真治 | 西田幾多郎の生涯と思想:西田哲学入門 |
| 12月9日、16日、1月13日 | 鶴 真一 | キリスト教とユダヤ教 |
| 基礎現代文化学系ゼミナール I (木曜日 5時限 文学部 新7講) | ||
| 10月14日、21日 | 田中 泉吏 | 生物学から世界を眺める:科学哲学への誘い |
| 10月28日、11月4日 | 杉本 舞 | コンピューティング史入門:『世界最初のコンピュータ』とは? |
| 11月11日、18日 | 井上 治 | 近代日本における芸道思想の展開 |
| 11月25日、12月2日 | 小林 敦子 | 1930年代の思想と文学 |
| 12月9日、16日 | 川嵜 陽 | 帝国日本と植民地朝鮮:朝鮮にとっての日本、日本にとっての朝鮮 |
2010年度文学研究科プレFDプロジェクト前期研修会
- 日時
- 2010年8月5日
- 場所
- 百周年記念時計台国際交流ホールII・III
- プログラム
-
- 開会式
- 開会の挨拶:FD研究検討委員会委員長 教授 田中 毎実
司会:高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
- セッション1
- 自己紹介
参加者の自己紹介と公開講座を担当しての感想
- セッション2
- ビデオ視聴
講義ビデオの視聴
- セッション3
- 個人ワークと発表
ワークシートとリフレクションシートを用いた自分の講義の振り返り
解説:高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之
- セッション4
- 学生の声の紹介
受講生に対するインタヴュー結果の紹介
文学研究科 教務補佐員 小城 拓理・三宅 岳史
高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之
- セッション5
- ミニ講義「大学授業をどう創るか」
高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代
- セッション6
- ・グループディスカッション

テーマ1:授業におけるメディアの活用
高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
テーマ2:「学生の多様性にどのように対応するのか」
高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之
テーマ3:「学生を学びに動機づけるには」
高等教育研究開発推進センター 特定助教 及川 恵
テーマ4:「学びを促す教材づくり」
高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代
・グループのまとめ
- セッション7
- 全体ディスカッション&まとめ
司会:高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之
- 閉会式
- 閉会の挨拶:文学研究科長 教授 赤松 明彦
修了証授与:FD研究検討委員会委員長 教授 田中 毎実
情報交換会
2010年度文学研究科プレFDプロジェクト後期研修会
- 日時
- 2011年2月24日
- 場所
- 吉田南1号館
- プログラム
-
- 開会式
- 開会の挨拶:FD研究検討委員会委員長 教授 田中 毎実
司会:高等教育研究開発推進センター 特定助教 田川 千尋
- セッション1
- 自己紹介
参加者の自己紹介と公開講座を担当しての感想
- セッション2
- ビデオ視聴
講義ビデオの視聴
- セッション3
- 個人ワークと発表
ワークシートとリフレクションシートを用いた自分の講義の振り返り
解説:高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
- セッション4
- 学生の声の紹介
受講生に対するインタヴュー結果の紹介
文学研究科 教務補佐員 小城 拓理・溝上 宏美・杉山 卓史
高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之
- セッション5
- ミニ講義「大学授業をどう創るか」
高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代
- セッション6
- ・グループディスカッション
テーマ1:「学生の多様性にどのように対応するのか」
高等教育研究開発推進センター 特定助教 半澤 礼之
テーマ2:「学生をどう授業に巻き込むのか」
高等教育研究開発推進センター 特定助教 及川 恵
テーマ3:「学びを促す教材づくり」
高等教育研究開発推進センター 教授 松下 佳代
・グループのまとめ
- セッション7
- 全体ディスカッション&まとめ
司会:高等教育研究開発推進センター 准教授 田口 真奈
- 閉会式
- 閉会の挨拶:文学研究科長 教授 佐藤 昭裕

修了証授与:FD研究検討委員会委員長 教授 田中 毎実
情報交換会
文学研究科プレFDプロジェクトを振り返って
各系のコーディネーターから
行動・環境文化系のゼミナールでは、前期・後期とも各専修(心理、言語、社会、地理)から数名ずつの講師に各2回ずつ、自分の研究 を紹介する内容の講義をしてもらった。パワーポイントを使った講義が多く、内容が豊富であるだけでなく面白くかつ分かりやすく、受講者の評判も悪くなかった。2回の講義を見る限り、どれもさして改善の余地があるように思えないほど完成された印象を与える立派な講義であった。今後の課題は、概論のような講義を1 年ないし半年にわたって教え続ける基礎体力作りと、講義の内容を理解するための努力を受講生からどのようにして引き出すかであるように思われた。また受講者の立場から考えると、行動・環境文化系の4 つの専修の、統一性のない講義の連続がどれほど受講に耐えるのか心配になった。なお講義を担当する人たちからは、いろいろな専門の話を聞けて良かったという声が聞かれた。(行動・環境文化学系ゼミナールコーディネーター 文学研究科:吉田 豊)
思想文化系前期はほとんど哲学史の全時期をとりあつかう重厚なプログラムだったが、授業を参観し授業後の検討会にも出席してみて強く感じたのは、講師の真摯な態度と有能な補佐員に支えられたプレFDの成熟だった。実はコーディネーターが心配したのは、講師があまりに自分の研究最前線を語りすぎて、受講者が置き去りになるのではないか、ということだった。その心配はほとんど杞憂だったというのが私の印象である。実際、講義は高度の内容を含んでいた。しかし検討結果をすぐに共有化しフィードバックする補佐員と講師の努力によって、受講者のリフレクション・シートには難解さを嘆くものはあまり見当たらなかったのである。こうした授業を受講する学生はそもそも一回生でも少々歯ごたえのあるものをもとめていたのではないか、という感じがした。この意味でプレFDは私にとって、文学部の学生とODに敬意をあらたにする機会にもなったのである。これは想定外だった。
(哲学基礎文化学系ゼミナールコーディネーター 文学研究科:福谷 茂・吉岡 洋)
基礎現代文化学系ゼミナールは、1、2回生のための導入的専門科目であり、博士課程を修了した若手研究者が、自分が現におこなっている研究をふまえつつ、後輩達に対して現代文化学系の学問についてわかりやすく講義することを目的としている。
このような授業には「相互に関連性のうすいこまぎれ授業となり、体系性に欠ける」デメリットが予想され、私もそれを危惧していた。しかし、実際に2年間授業を参観してみると、必ずしもデメリットとはいえないと気づかされた。そもそも現代文化学なるものに定形はなく、極端に言えば、この授業を担当しているような若手研究者層が、それぞれの時代感覚と学問意識にもとづいて日々実践してきたその研究営為の総体によって形作られるものである。その多様な断面を提示することは、まさに現代文化学の核心を伝えるものにほかならないのだ、と。
そう感じるにいたったのは、もちろん講師達が授業に注いでくれた熱意と努力のおかげである。彼等は、初学者である学生に向けて伝えるには、研究とは異なる論理展開やデータの処理が必要であることをよく理解し、さまざまな工夫をこらした。プレ FD プロジェクトに参加していなければ、おそらくこれほど高い教育意識はもちえなかったのではないか。これからの大学教育の第一線を担うのは彼等であることを考えると、これこそがFDであろう。
(基礎現代文化学系ゼミナールコーディネーター 文学研究科:永井 和)